バクラク申請・経費精算でエンジニアをしています三角 (@delta) です。
「これは面白そう!」と思って買った本が意外と難しく、気づけば読むことなく本棚の肥やしに…。一度はそんな経験があるのではないでしょうか。私もその一人です。 そんな方におすすめなのが読書会です。読書会を通じて自分が本の中の知識を得ることはもちろん、交流を深めること、組織のレベルアップもできます。たくさん嬉しいですね。
この記事では、私がよくやっている読書会のやり方を紹介します。
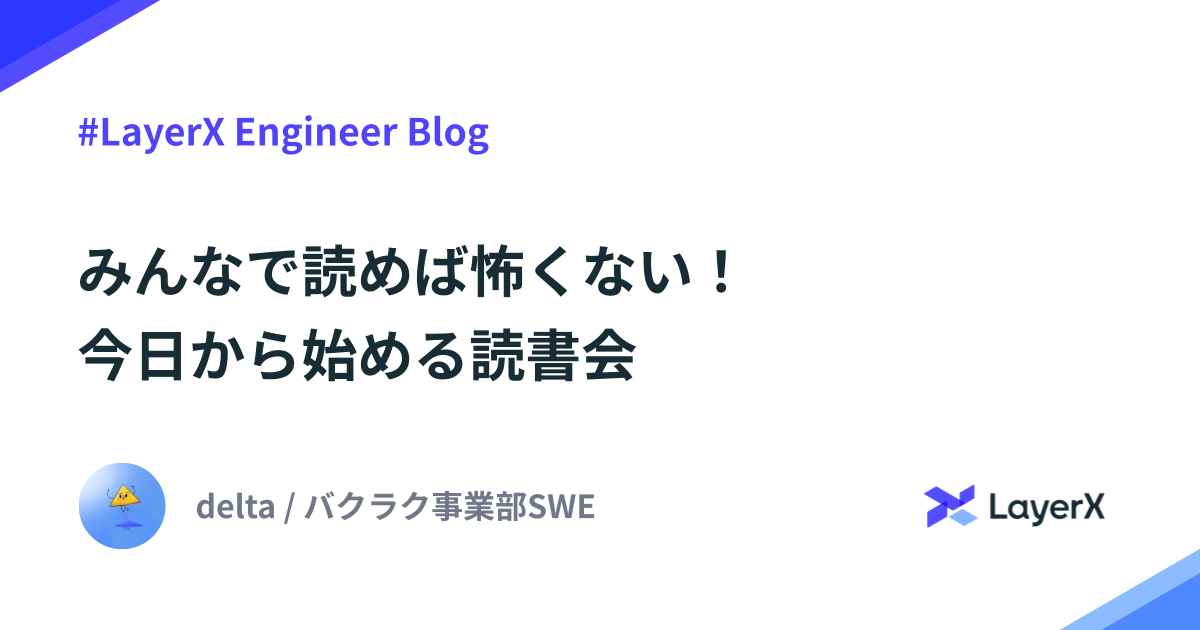 ※記事中で扱っている内容はあくまで私が過去に参加/主催した読書会の内容も含めて総括的に書いたもので、全てが LayerX 社内で取り組んだ内容だけではありません。
※記事中で扱っている内容はあくまで私が過去に参加/主催した読書会の内容も含めて総括的に書いたもので、全てが LayerX 社内で取り組んだ内容だけではありません。
1. 目的を決める
最初に目的を決めましょう。 過去に私が取り組んだ読書会だとこの辺りを目的にしていました!
- この本に自分の今取り組んでいる仕事に近い内容が載っている
- 新しい技術のキャッチアップをしたい
- 社内の技術レベルを上げたい
- チーム内の共通認識を持ってレベルアップしたい
- 純粋関数型に触れたい
2. 一緒に読む人を募る
目的が決まったら声をかけましょう。集まらなかったら開催しないだけなのでここはビビらず募りましょう。 ちなみに集まらなかったことは自分は今まではなかったです。 意外と一人だと読めないから参加しようとなる人は多いと思います。
3. 本を決める
本を決めましょう。本ありきで目的が決まっていることもあれば、目的に沿って本を決めるもよし、参加する人で集まって本を決めるでもいいと思います。 基本的には割とサクッと決まりますが、もし迷ったときの tips として「総ページ数が少ない」「章立てが細かい」のいずれかを満たしている本だと読書会がダレずにすみます。
4. 読み方を決める
読み方を決めましょう。ここが一番大変です。 私が参加した読書会では主に「本の内容を個々人が理解する」「個々人の理解をより深める」の 2 つの時間を取っています。 この 2 つのバランスも読書会の目的や本の種類によって柔軟に考える必要があります。
ケーススタディ的にこちらも過去やったやり方を書いておきます
| 目的 | 読んだ本 | 参加者(人数) | 本の内容を個々人が理解する時間 | 個々人の理解をより深める |
|---|---|---|---|---|
| 純粋関数型言語を触ってみたい | すごい Haskell たのしく学ぼう! | チームを跨いだ社内の有志(4 人) | 章ごとに参加者で順番に Jupyter Notebook に sample code と簡単なメモを書いてきて発表してもらう | 分からない部分をその都度挙手制で確かめる |
| 社内のエンジニアのレベルの底上げをしたい | Effective Python ―Python プログラムを改良する 59 項目 | チームを跨いだ社内の有志(20 人) | 章ごとに参加者で順番に Jupyter Notebook に sample code と簡単なメモを書いてきて発表してもらう | 分からない部分を発表後挙手制で確かめる / 社内で使っている箇所や有効的に使えそうな場面について話す |
| チームのプラダクトマネジメントのレベルアップをしたい | INSPIRED 熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント | チームメンバー(7 人) | 読書会前に事前に読んでくる | miro に付箋を貼ってチームの現在地とのギャップを確認する |
| アーキテクチャについてもっと考え方の手札を増やしたい | Tidy First? ―個人で実践する経験主義的ソフトウェア設計 | チームを跨いだ社内の有志(10 人) | 読書会前半で個々人で黙読 | miro に付箋を貼って分からなかったことを話す / 各チームでの取り組みを話す |
他にも必要な箇所だけ章をピックアップして読むなどの工夫も効果的だったのでぜひ取り入れてみてください。
パッと思いつく皆んなで音読しあう形式も何度かチャレンジしましたが、文章量の多い本という媒体だと音読している人が音読に集中して頭に入ってこない、聞いてる人も聞いてる気になって頭に入ってこないみたいな誰も嬉しくない状態になりやすいと思い個人的にはあまりお勧めしません。
読書会で取れる時間はある程度は決まっていると思うので、「個々人の理解をより深める」に重きを置く必要がある場合は「本の内容を個々人が理解する時間」を読書会の時間では短く収まるようにする、本の中身を一周できれば良い場合は「本の内容を個々人が理解する時間」を読書会の時間のメインにするみたいな感じで設計するのがいいと思います。
5. 振り返り
終わったら参加者で本の振り返りと読書会自体の振り返りもサクッとやりましょう。 直近は前述の「Tidy First? ―個人で実践する経験主義的ソフトウェア設計」の読書会を社内でやりましたが、個人的な学びがたくさんあったのはもちろん、「miro で感想書きながら読むスタイル、記憶に残りやすくてよかった」「1人で読んでも解釈難しいところが多かったので、他の人の意見・解説を聞きながら理解できるのが良かったです!」など主催者冥利に尽きるコメントもあり嬉しかったです。
おわりに
どうでしょうか? なんだか「自分でもできそう!」な気がしてきませんか?一人だと難しくて挫折しそうな本も、みんなで集まって話しながら読めば、意外と楽しく読み進められます。 完璧な読書会を目指す必要は全くありません。大事なのは、まず一歩を踏み出してみること。この記事が、あなたのチームの「最初の一歩」のきっかけになれたら、とても嬉しいです。
LayerX では、ソフトウェアエンジニアをはじめとして様々な職種で仲間を求めています。もし少しでも興味がある!という方はぜひ以下からご応募ください!
X の @LayerX_tech アカウントでは LayerX の様々な取り組みを発信していますので、是非こちらもフォローしてください。