こんにちは、すべての経済活動をデジタル化したい makogaです。
幕間CMの動画を見た方はいらっしゃいますか?一部では「AIが話しているのでは?」という声もありましたが、実は私がAIっぽく話していました。
LayerXとYAPC::Fukuoka 2025
LayerXは、今回Perlスポンサー、ブース出展、企画LT賞に協賛しました。イベントを通じて多くの方と交流できたことを嬉しく思います。
tech.layerx.co.jp tech.layerx.co.jp
企画LT賞
たくさんの応募をいただき、誠にありがとうございました。当日は6名の登壇者によるLTが行われ、どれも素晴らしい内容でした。その中から、nikkieさんによる「Pythonを“理解”しているコーディングエージェントが欲しい!!」をベスト企画LT賞として選出しました。おめでとうございます!
今回の「ベスト企画LT賞」は...@ftnext さんの「Pythonを"理解"しているコーディングエージェントが欲しい!!」です!
— LayerX Tech (@LayerX_tech) 2025年11月14日
おめでとうございます👏https://t.co/NP8yRstIMI#yapcjapan #yapcjapanA pic.twitter.com/AzbDyni9C2
発表スライド: ftnext.github.io
ブース出展
YAPCのTrackBは本日から企業ブースになります!
— LayerX Tech (@LayerX_tech) 2025年11月15日
LayerXのブースは入り口から見て正面奥です。
エンジニアや本日登壇のメンバーもブースにいますので、ぜひお立ち寄りください!#yapcjapan pic.twitter.com/BxkjkdfI1n
LayerXのブースには多くの方が訪れてくださいました。エンジニアや登壇メンバーも参加し、AIエージェントへの投票企画も大いに盛り上がりました。
「1.5年後に当たり前に使われているAIエージェントは?」というテーマのもと、来場者の皆さんに投票していただきました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!
YAPC::Fukuoka 2025 現地参加された皆さま、お疲れ様でした!
— LayerX Tech (@LayerX_tech) 2025年11月15日
LayerX ブースにて実施していた「1.5年後に当たり前に使われているAIエージェントは?」にご回答いただいた皆さま、ありがとうございました!
ぜひ、また来年東京でお会いしましょう👋#yapcjapan pic.twitter.com/1lL7nfK7Tv
登壇者と登壇内容
今回は技術広報兼HRのserimaが登壇しました。
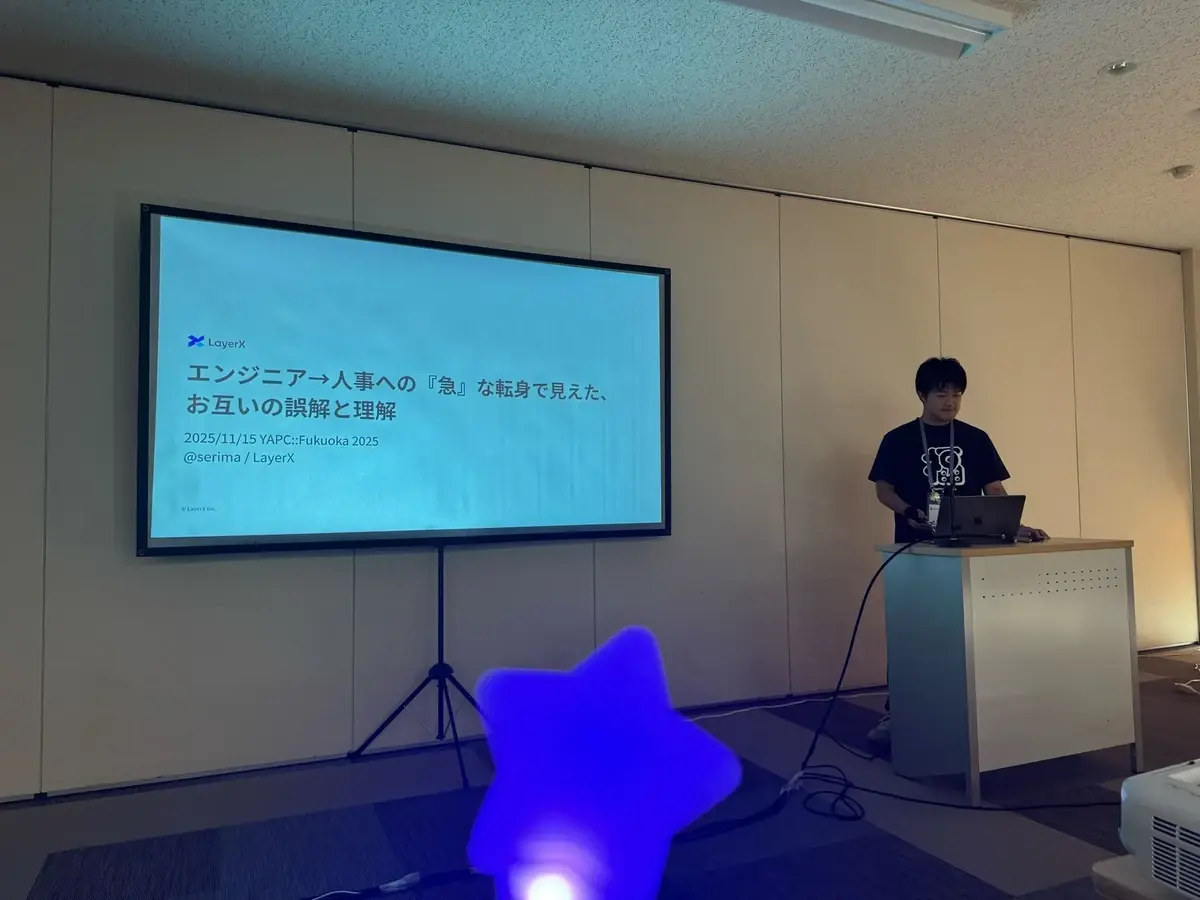
エンジニアから人事へのキャリア転換をテーマに、立場の違いによる誤解や、それをどう理解へと変えていったかを語りました。エンジニアと人事の橋渡しを担う立場ならではの視点が印象的でした。
さきほどの登壇資料を公開しました。聞いてくださった皆さま、ありがとうございました!
— serima | LayerX (@serima) 2025年11月15日
エンジニア→人事への『急』な転身で見えた、お互いの誤解と理解https://t.co/IW5dPXhOkQ #yapcjapan #yapcjapanC
印象に残ったセッション
現地参加したメンバーから、印象に残ったセッションについてコメントをもらいました。
Agentに至る道 〜なぜLLMは自動でコードを書けるようになったのか〜
Coding Agentが普及するまでに辿った道を論文を紹介する形でわかりやすく解説されていて、とても面白かったです。後半にはCoding Agentをライブコーディングで実装するコーナーがありました。普段利用しているClaude CodeなどのCoding Agentをより身近に感じるようになりました。
探求の技術
外部発信を継続するための仕組みづくりから、発信の質を高める工夫まで実践的な tips が紹介されていて、外部発信に苦手意識をもつ人にも、さらにレベルアップしたい人にも役立つ内容でした。
特に「記録は目に見える形で残すべきだが、その工程は必ず自動化すること」というポイントは、習慣化に何度も挫折してきた自分にとって参考になりました。手動の記録が途切れの原因になるという指摘には強い納得感がありました。
なぜわかりやすい記事を書けるのか、その秘訣は自分が対象を一番わかっていないことにある。ある分野に精通してから外部発信するのではなく、理解を深めていく過程を発信するべきとのメッセージもあり、発信に対する勇気をもらえました。
AIの弱点、やっぱりプログラミングは人間が(も)勉強しよう
AIの仕組みから、なぜAIがプログラムを書く時代になってもプログラミングを学ぶ必要があるのかが体系的に整理されていて、とても良かったです。より良いコードを書けるように頑張ろうという気持ちになりました。
大規模OSSに一人で立ち向かうには
いろんな困難はありながらも、情熱を持って、凡事徹底しながら技術に向き合い続けるという、エンジニアとして、そして人としてのかっこよさを感じました。「時間を可能な限り捻出して、可能な限り時間を使うこと」「わからないことを本気で理解しにいくこと」を徹底しながら、初心を忘れず情熱を持って自分も技術と向き合っていきたいと思いました。
伝統的日本企業のソフトウェアエンジニアになって無双しよう!
これに尽きる。すごく良い理念。
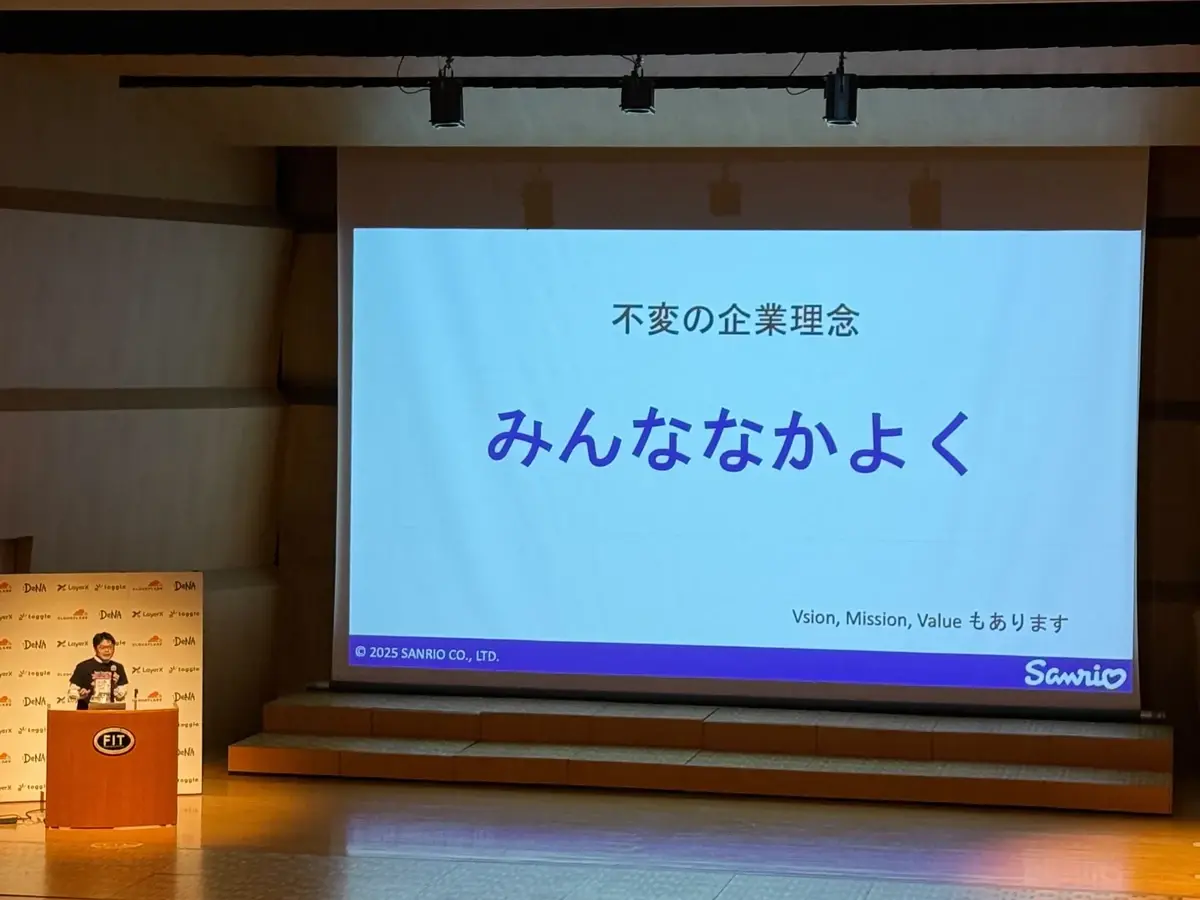
日本の非常に巨大な企業の中で、対話でお互いを理解しながら、あるべき姿に進んでいく話でした。LTなので面白おかしく話すトーンでしたが、裏にある努力や会社を良くしていこうという強い思いを感じました。
おわりに
YAPC::Fukuoka 2025では、AI・エンジニアリング・発信文化といった多様なテーマが交差し、たくさんの刺激を受ける2日間となりました。登壇者・参加者・運営の皆さま、本当にありがとうございました。来年もまた現地でお会いできることを楽しみにしています。